市販薬濫用問題に対する産官学の取組み
このページの内容は薬事ニュース第4735号(2025年8月1日)に掲載されている内容になります。
近年、10代~20代の若者を中心に、咳止めや風邪薬など市販薬の濫用(いわゆるオーバードーズ〈OD〉)が急増し、大きな社会問題となっている。薬機法改正案において「濫用等のおそれのある医薬品の販売方法の厳格化」が示されるなど、薬事規制の側面からも対策の確立が進んでいる。こうした中、この問題を真摯に受け止め、独自の取組みを進める企業や行政などの動きがある。本特集では、それぞれの取組み内容を紹介するとともに、彼らがどのような使命をもって対応しているのか、その想いについても伝えたい。
シオノギヘルスケア 当事者に寄り添いながら、取組みを推進していく
■濫用問題に関して3つの取組み
シオノギヘルスケアは渦中の製薬企業の1つとしていち早く実態調査に乗り出し、社内プロジェクトを発足。独自の対策として▽適正な医薬品アクセス基盤▽OD当事者への寄り添い▽濫用予防に向けたくすり教育支援――の3つの取組みを進めている。同社製品保証本部 信頼性保証部 学術・規制グループの笠松良治氏は、この前提として「いわゆる『トー横』『グリ下』『ドン横』の実態調査を試みた」という。その中で「実際に自社の薬の空箱が捨てられていたのはショックだった」との率直な意見を述べた。また同時進行で、厚生労働省「医薬品の販売制度に関する検討会」において参考人として市販薬濫用の実態を報告した嶋根卓也氏(NCNP)を始めとする研究者らや、OD当事者らと意見交換を進め、「全体像を網羅的に把握した上で、浮かび上がってきたのが3つの取組みだった」と述べた。
■空箱設置で一定の効果
このうち「適正な医薬品アクセス基盤」の取組みでは、「東京、大阪、愛知の特定地域において、濫用者が容易に手の届かない環境を作ることが必要だと考えた」とし、「盗難防止という観点、また薬剤師などの有資格者との接点につながるゲートキーパーの役割になるという観点、これを狙いとして、空箱の設置策を講じた」と説明。一方で笠松氏は「当時は空箱で販売するという店舗はあまりなく、最初はなかなかうまくいかなかった」と話す。それでも「雨の日も、雪の日も、毎日直接店舗へ出向き、今の実態を丁寧に説明し、協力依頼を進めてきた。風向きが変わったのは2024年の制度部会での議論が進んだ辺りからだった」と振り返った。
なお同社は空箱設置後、2か月間(2024年5月-6月)の効果検証も行っている。特定地域計239店舗のうちヒアリング可能な薬局薬店において、盗難がなくなった店舗割合は56%(32/57店舗)、複数購入がなくなった店舗割合は73%(33/45店舗)、濫用者の来店が減少した店舗割合は54%(31/57店舗)となった。笠松氏は「この結果から、空箱の設置は一定の効果が得られたと考えている」とし「この結果をもって、空箱の設置の意義を店舗様に伝え、さらに空箱の浸透を進めていきたい」との展望を述べた。
■当事者を適切に「つなげる」仕組みづくり
また「OD当事者への寄り添い」では、前述のOD当事者らとの意見交換において「本当はODから抜け出したいと思いながら、抜け出すことができない方が一定数いることがわかった。その方々にしっかり手を差し伸べる必要があると考えた」とし、濫用者に向けた正しいケアの発信と、そのケアを提供できる専門機関・窓口との接点づくりを実施。薬物依存からの回復と社会復帰を支援するNPO法人DARCとの共催で、OD当事者およびその家族に向けたセミナーを開催した。さらに同社の製品パッケージに適切な専門機関および窓口へ「つながる」QRコードを記載したほか、同QRコードを店舗に配置できる名刺サイズのメッセージカードに印刷した「ツナグカード」を作成し、OD当事者が相談窓口へ「つながる」きっかけづくりを後押ししている。笠松氏は「実際にODで苦しんだ方々と意見交換を行いながらメッセージの文言や、フォント、イラストの作製を進めた」とし、配布場所について「現在は龍生堂の全店舗に置かせていただいている」と説明。「OD当事者に適切なケアが届くことを目指しながら、私たちは仕組み作りを進めたい」と述べた。
■低学年からの市販薬くすり教育に向け
さらに「濫用予防に向けたくすり教育支援」では、大学以外の学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)に常駐する「学校薬剤師」を支援。危険ドラッグや大麻といった指定薬物に関する教育だけでなく、市販薬を正しく使うことを基本に、濫用される薬物が人体に与える有害作用等までを説明し、薬物濫用防止活動として「くすり教育」を担う三重県薬剤師会の学校薬剤師の活動について、東海薬剤師学術大会で共同発信した。笠松氏は「これまで市販薬の濫用問題に関するくすり教育というのはあまりされていなかった」ことに加え「実際にどのようにくすり教育の授業を進めたらいいか分からないというご意見もいただいた」という。「三重県薬剤師会学校薬剤師の方々の活動を日本薬剤師会学術大会で発信することで、市販薬のくすり教育をサポートしていきたい」との思いを述べた。
■継続して取組みを推進
同社は加えて、製品パッケージや容器、販促物にPOPシールや情報提供資料等を掲載し、適正使用に向けた工夫を徹底している。さらに今後も市民向けのセミナー活動を継続していくという。笠松氏は「濫用問題に関して、私たちができるのはほんの少しのことかもしれない。根本的な解決はもっと別にあるかもしれない。それでもできるだけ当事者に寄り添いながら取組みを推進し、根本のところにも働きかけていきたい」と話す。「今後も、まだ浸透していない地域への空箱設置や、ツナグカードの配布を進めていく。さらに三重県薬剤師会等の成功事例が横展開で広がるよう、支援を続けていく」との強い想いを語った。
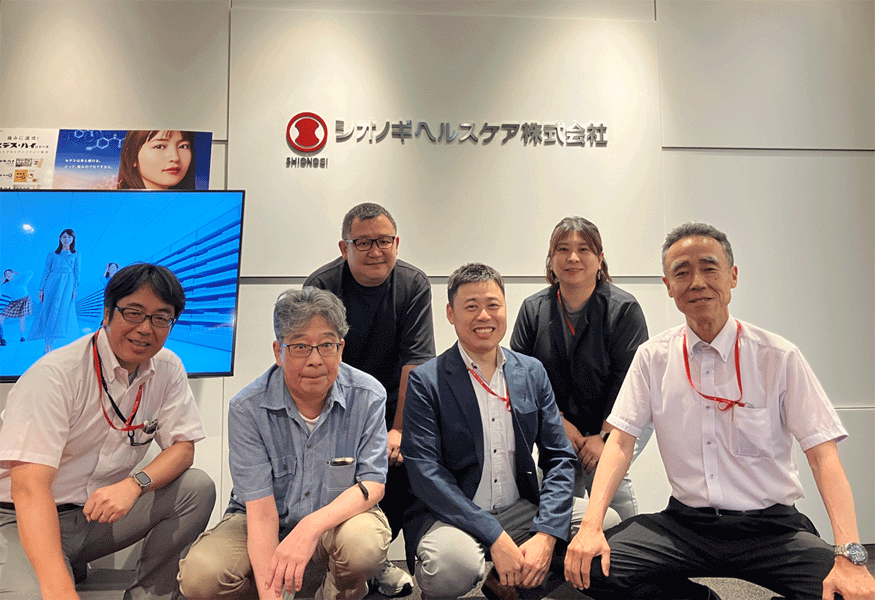 |
| 社内プロジェクトのメンバー |
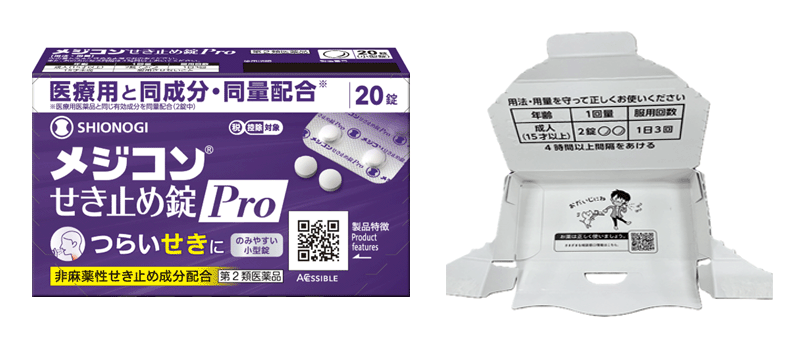 |
| 実際の製品パッケージ。包装内にQRコードを配置している |
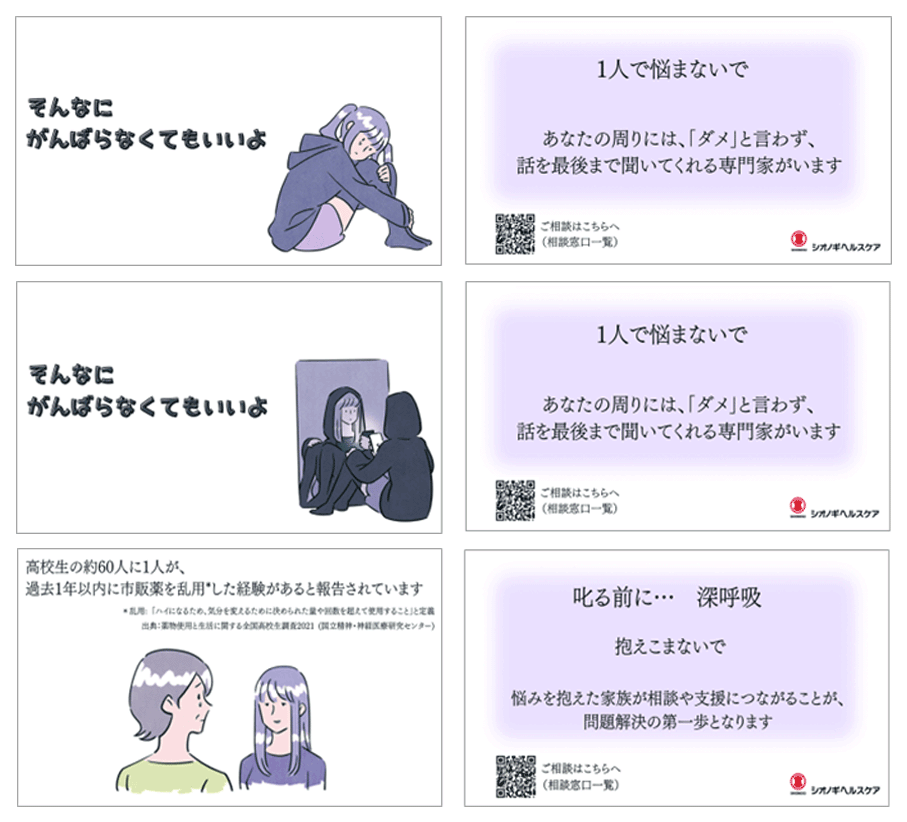 |
| ツナグカードは当事者向け2パターンに加え保護者向けも |
 |
| 共催セミナーの様子 |
国立精神・神経医療研究センター 「背景にある事情を見つめて理解することが大切」
精神保健研究所 薬物依存研究部 心理社会研究室 室長 嶋根卓也 氏
嶋根氏は一般用医薬品(OTC薬)の濫用や薬物依存に関する実態調査を専門とし、厚生労働省より委託され政策立案や規制強化にも関与しているこの分野の第一人者。「私たちは2021年に高校生対象の全国調査を行ったが、ODの経験がある高校生は、約60人に1人の割合で存在することがわかった。またOTC医薬品の濫用率は、従来、予防教育の対象になっている違法薬物と比べても10倍ぐらい高い。高校生にとってOTC医薬品の濫用がとても身近にあること分かり、非常に驚いた」と話した。さらに調査を進め、OD経験のある高校生と、ない高校生とを比較したところ、OD経験のある高校生は「社会的な孤立状態にある人が多いということが分かってきた」という。嶋根氏は「彼らがなぜODをせざるを得ないのか、その背景にある事情をきちんと見つめて理解することが大切だ」と声を強めた。課題の一つとして「専門医療機関を受診するハードルの高さ」を挙げ、「例えばLINEを活用したSNS相談など、10代の若者でも気軽に利用できる相談サービスもある。こうしたサービスの認知度をより上げることが大事だ」と述べた。また「ODに関する啓発ポスターを掲示する薬局や、シオノギヘルスケアのツナグカードを配布する薬局もある。これらに加えて依存症の相談機関等のリーフレット設置も必要ではないか。また頻回に買いに来る方には、一歩踏み込んだおせっかいをするという、いわゆるゲートキーパーとしての介入も重要だ」と述べた。ゲートキーパーの対応については今年3月、厚生労働省が「ゲートキーパーとしての薬剤師等の対応マニュアル」を公表。同マニュアルは嶋根氏を始め日本薬剤師会の富永孝治氏らが参加した「一般用医薬品の乱用防止対策WG」が制作監修している。嶋根氏は「日本薬剤師会など、各団体からこのマニュアルが各店舗へ広がることを願っている」と述べた。また嶋根氏は厚生労働科学研究として「大手チェーンドラッグストアにおける市販薬販売の実態に関する研究」を実施している。研究ではゲートキーパー研修プログラム(GKTP)全コンテンツを提供されたA群と、一部コンテンツを提供されたB群とでランダムに割付けて、介入前と介入後の変化について比較している。研究は進行中だが、令和6年度段階での報告では「GKTPを受講することで、市販薬の濫用問題に対する理解が深まり、濫用リスクのある患者に気づき、対応する上での自己効力感が増加するなどの効果が確認されている」という。なお研究は今年度が最終年となる。嶋根氏は「プログラムを受講した薬剤師にどのような変化があったのか、結果が楽しみだ」と述べた。
嶋根氏は並行して全国の依存症専門医療機関を受診した患者を対象とする研究を進めているが、今後の課題として「濫用のおそれのある成分に『デキストロメトルファン』を入れる必要があるというのが、私たちの研究の結論。もう一つ議論すべきとしてアリルイソプロピルアセチル尿素、ブロモバレリル尿素などの成分を一般用医薬品として継続使用することが適切なのか、という問題だ」と指摘した。また「カフェインについても一律で規制するのは現実的ではない。販売方法について議論の必要があるのではないか」と述べた。
大阪府健康医療部生活衛生室薬務課 「正しい薬の使い方を広げることが最大の目的」
大阪府健康医療部生活衛生室薬務課 医薬品流通グループ 課長補佐 嶋田慎一 氏
大阪府健康医療部生活衛生室薬務課 医薬品流通グループ 統括主査 関根温子 氏
【嶋田】 私たちは今年3月に「薬剤師・登録販売者の資質向上のための実践ガイド」を作成した。 同ガイドは一般用医薬品の販売に関わる薬剤師および登録販売者に対し、濫用防止に向けた具体的な取組みを示すもので、大阪府薬務課に加え、府内の薬剤師会や薬局、製造販売業者の取組み事例も紹介している。さらに大阪府薬務課では薬剤師および登録販売者向けに販売時のルールや濫用の実態、相談窓口を掲載したリーフレットを作成する等、濫用防止に向けた取組を行っている。
【関根】 作成にあたっては府内の医師会や薬剤師会など関係団体の方々が参加した大阪府薬事審議会医薬品適正販売対策部会で議論を進めてきた。府内の薬局や店舗販売業などへ活用いただけるよう、ガイドは大阪府薬務課のHPにも掲載している。またガイドを製本化し、研修会で配布している団体もあると聞いている。
【嶋田】 私たち薬務課としては、「正しい薬の使い方」を広げることが最大の目的。まずは府内の店舗で濫用問題についてきちんと認識してもらった上で、プロとして適正に販売していただきたいというのが切実な思いだ。一方で、法律で義務付けられてはいないが、いわゆる OD対策にあたって重要な観点である「ゲートキーパーの役割」についても考えてほしい。ODというのは、当事者にとって心を守る手段。であるならば、きちんと相談窓口や、あるいは必要な医療につなげていくことが必要だ。
【関根】 これまでも府民に向けたイベントや、相談窓口につなぐためのターゲティング広告などを実施してきたが、今後も引き続き同様の取組みを通じて府民に向けた啓発活動を行っていきたい。大麻といった違法薬物ではないものの、一般薬も適正使用を損なえば毒にもなる。恐怖感を植え付けるのではなく、正しい薬の使い方や知識を啓発していきたい。
三重県薬剤師会 「適正使用を訴えることが私たちの使命」
三重県薬剤師会理事・三重県学校薬剤師会会長・はった薬局 郷幸代 氏
三重県薬剤師会理事・三重県立こころの医療センター診療技術部技師長 中村友喜 氏
【郷】 学校薬剤師は、学校で児童や教職員の方々が健康に過ごすため、学校環境衛生の維持管理に従事している。その一環として私たちはくすり教育を実施してきた。これまでは覚せい剤や大麻、タバコに関する授業を行うことが多かったが、近年は市販薬濫用防止の観点における「くすりの正しい使い方・薬物乱用防止教室」の展開を始めている。2024年には三重県内の198校で開催し、1万5000人ほどの学生、生徒に授業を聞いてもらった。
【中村】 私は以前からこころの医療センターで依存症治療に携わってきたが、近年、当院のAYA世代病棟にもODに関わる患者さんが増えてきた実感があったため、学校におけるくすり教育の重要さを感じ、三重県薬剤師会の活動に協力し始めた。
【郷】 授業では「なぜ薬は決められた用法用量を守る必要があるのか」という座学に加え、「薬をジュースで飲んだらどうなるか」などの実験を行い、薬を正しく使うことの重要性を伝えている。これからはセルフメディケーションの時代。将来に向けて今から何がやれるかといったら、くすり教育を通じて適正使用を訴えることが私たちの使命。必ず将来に役立つと考えている。
【中村】 授業の前後にアンケートを行っているが、アンケートからは、最初はあまり興味がなかった生徒たちが、最後には興味深く授業を終えたことがみえてくる。中には「今までは誰にも相談できなかったが、相談してみようと思った」という意見もあり、授業を行うことの重要性を痛感している。一方で、今後はこの活動を学校薬剤師だけではなく、子どもたちの心の問題に対するアプローチにつなげていかなければならないと感じている。
龍生堂 「店舗とメーカーが協力し情報提供を続ける」
龍生堂本店 大久保エリアマネージャー 医薬品登録販売者 吉村賢一 氏
龍生堂では商品の空箱化や店頭でのポップ・ポスターの掲示に加え、これまでも行ってきた業務手順書を明確化し、販売時に「医療機関の受診の有無」や「他の医薬品の使用状況」など13項目の確認を徹底した。さらに濫用に該当する成分に関してレジでアラートを鳴らし、口頭説明を行っている。吉村氏は「店頭で一度声をかけることが一定の抑止力になっているという手応えがある」と述べた。
また同社は、「OD当事者に寄り添う活動」にいち早く取組み、適切な専門機関および窓口へ「つながる」QRコードを記載した名刺サイズのメッセージカード(ツナグカード)を店頭に設置している。吉村氏は「いわゆる濫用の対象となる薬の近くにカードを設置しているほか、該当商品を購入した方にお渡ししている。利用方法はまだまだ手探りだが、こういった活動をきっかけにOD当事者の心を掬い上げる一助になれば」と話した。加えて「店舗とメーカーが協力して、お客様へ一貫した情報提供を続けていくことが、その先につながっていくだろう」との展望を述べた。
 |
| 手に取りやすい場所に「ツナグカード」を配置 |
 |
| 店頭には啓発ポスターも掲示している |